おはようございます。
中小企業診断士のシンです。
本日はいよいよ事例ⅠH29年度問題の最後「2次試験対策 事例Ⅰ H29年度解答作成まで」です。
まずは過去記事です。
「2次試験対策 事例Ⅰ H29年度 与件読んでみた①」「2次試験対策 事例Ⅰ H29年度 与件読んでみた②」は下記です。
俯瞰して考える・診る
昨日の記事までが前工程で、本日は後工程となります。
前工程は解答を構成する上の準備。
前工程までが80分の内40分ぐらいまでに出来れば80分間での解答に間に合います。
設問解釈のやり過ぎ、与件解釈の深堀すぎ、サイン・マークのつけすぎで疲弊してしまっては、この後の解答作成で頭が回らなくなります。
ここで一息。俯瞰して全体を見る目、鳥の目が必要です。
敢えて、全体像を見る。
情報過多の場合、頭が回らない状態になります。
中小企業診断士が必要な能力は。「診る・聞く・書く。」
2次試験では聞くが読む・読み込むになり、診る工程がこの瞬間です。
解答構成
設問分析時に解答構成を決めておくパターンと、与件分析と対応付けの後に解答構成を決めるパターンがあります。
書き出しと書き終わりのある程度のイメージ、文章の数と構成は、字数によって事前にパターン化していた方がよいです。
書く訓練はまた別の記事で書かせていただきます。
H29年度試験事例Ⅰ 全国市場への進出を目指す、菓子製造業
引き続き平成29年度試験事例Ⅰを使用して対応付けのまとめと解答構成について解説をしていこうと思います。
この年の企業は「菓子製造業」で、設問は5題でした。

※設問、【出題の趣旨】、<対応付ける段落>、「キーワード」『1次知識』コメントの順で1問ごとに記載していきます。
第1問 配点20点
景気低迷の中で、一度市場から消えた主力商品をA社が再び人気商品にさせた最大の要因は、どのような点にあると考えられるか。100 字以内で答えよ。
時制は「過去」。経営戦略問題。情報の整理・分析。類推問題。
☆解答構成
(最大の)要因は~〇〇。〇〇して、〇〇~こと。
最大の要因という縛りを無視せず1つのことをブレずに伝えているように書きまとめる。
【出題の趣旨】
第 1 問(配点 20 点)
創業後わずかな期間で高い業績をあげるに至った要因について、経営環境を考慮した上で分析する能力を問う問題である。
→「経営環境を考慮した上で分析」 と記載があります。
※出題の趣旨は、中小企業診断協会のHPに試験後にアップされています。
経営環境はSWOT分析。
事例問題を解く時に「SWOT分析」をしてから解くやり方もあると思います。
自分の場合はS強みO機会を赤オレンジ黄色の暖色系、W弱みT脅威を青・水色の寒色系のマーカーで色づけて視覚的に判断しました。
<対応付けた段落>
第1・3・4・5・6段落と広く対応付けました。
核となるのは3・5段落。
「キーワード」
第1・3段落「地元で認知度が高い」
第4段落「商標権」「経営支援の継続、商品の存続」
第5段落「主力商品だけに絞って」「商品を冠にした新会社設立」「昔ながらの味」
『1次知識』
キーワードと1次知識を使って、1つのことを一貫して言っているように文章にまとめる。
第2問 配点20点
A社の正規社員数は、事業規模が同じ同業他社と比して少人数である。少人数の正規社員での運営を可能にしているA社の経営体制には、どのような特徴があるのか。100 字以内で答えよ。
時制は「現在」。経営戦略問題。情報の整理・分析。
☆解答構成
特徴は〇〇なこと。〇〇~なこと。1文か2文にまとめる。
【出題の趣旨】
同業他社に比べて少数の正規社員による効率経営を実現している事業の仕組み及び管理体制について、分析する能力を問う問題である。
→少数の正規社員による効率経営、事業の仕組み及び管理体制が追加情報。
<対応付けた段落>
第1・2・5段落。
核となるのは3・5段落。
「キーワード」
第1・2段落「非正規社員」
第2段落「補助業務」↔「コア業務」
第5段落「主力商品だけに絞って」「自動化」「効率性を高められた」
『1次知識』
正規社員と非正規社員の経営戦略上のメリット、アウトソーシング
キーワードを使って非正規社員の有効活用についてまとめる。
第3問 配点20点
A社が工業団地に移転し操業したことによって、どのような戦略的メリットを生み出したと考えられるか。100 字以内で答えよ。
時制は「過去」。経営戦略。情報の整理・分析。
戦略的メリットを書く。
☆解答構成
(メリットは)〇〇なこと。〇〇~できた。2文にまとめる。
【出題の趣旨】
第3問
事業活動拠点の移設に伴う事業展開上の戦略的メリットについて、分析する能力を問う問題である。
→言い代えで追加情報なし。
<対応付けた段落>
第6段落。
「キーワード」
第6段落「地元の企業を誘致対象とした工業団地」
「食品製造の国際標準規格、HACCAPに準拠」「日産50,000個体制にまで構築」
『1次知識』
規模の経済性、オープンイノベーション
主に6段落の内容をまとめ、今後の事業展開の話にもっていく。
第4問 配点20点
A社は、/全国市場に拡大することで/ビジョンの達成を模索しているが、/それを進めていく上で/障害となるリスクの可能性について、/中小企業診断士の立場で助言せよ。/100 字以内で答えよ。
時制は「未来」経営戦略。助言問題。
☆解答構成
リスクは〇〇なこと。〇〇~なこと。2文にまとめる。
【出題の趣旨】
第4問 配点20点
地域ブランドとして優位性をもつ主力商品の全国市場への展開がもたらす問題を分析し、それに対して適切な助言をする能力を問う問題である。
→問題と助言の問題。リスクを単に列挙するんではなく、診断士の知識を使って助言する必要もあったという解釈。
<対応付けた段落>
第1・7段落。
「キーワード」
第1段落「非正規社員」
第7段落「全国市場への進出」「首都圏出店」「主新商品の開発」「人材の確保や育成」
『1次知識』
経営資源の分散
リスクを助言せよ。リスクだけを書くのではなく、対応策を書いても助言になる。
第5問 配点20点
「第三の創業期」ともいうべき段階を目前にして、A社の存続にとって懸念すべき組織的課題を、中小企業診断士として、どのように分析するか。150字以内で答えよ。
組織構造、組織文化、人的資源管理の全てを活用。
☆解答構成
150字と字数が多いので、〇〇~な中、〇〇する、〇〇する、〇〇する。3つぐらい施策を入れる。
①、②、③とナンバリングする作成もあります。
自分は始めはナンバリングしてましたが、最終的には敢えてナンバリングはしませんでした。
【出題の趣旨】
第5問 配点20点
非同族支配の中小企業であるA社が、「第三の創業期」といわれる新しい時代に向けて、どのような経営課題に直面しているのかを分析する能力を問う問題である。
→非同族支配の中小企業と 経営課題に直面が追加された情報です。
<対応付けた段落>
第2・7・8段落。
「キーワード」
第2段落「機能別組織」
第7段落「全国市場への進出」「首都圏出店」「主新商品の開発」「人材の確保や育成」
第8段落「定年退職」
『1次知識』
機能別組織のデメリット 、組織変革・組織学習、人的資源管理(採用・配置・能力開発・評価)このうち正社員・非正規社員の採用・配置・能力開発
前提の状況「定年退職」している中、と状況を記載して、そのあとに1次知識を使った施策を複数列挙する。
機能別組織のデメリットに触れて、ノウハウの継承、人材・後継者の育成、を書いてもよいと思います。
解答の順番
解答の順番は第1問から第5問と解答しなくても大丈夫です。
成果物が出来ればよい。1次試験でも最初の問題から解くとバランスを崩すように、2次試験も難しい問題にはまって考え過ぎてしまうと、バランスを崩してタイムオーバーです。現実は厳しいですが、解きやすい問題から解いて先行逃げ切り型が理想です。
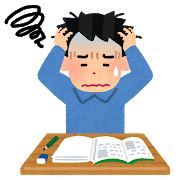
平成29年度(2017年度)の解答解説が掲載されている書籍
TAC
定番の過去5年間の過去問の解答解説
ふぞろい
2018年版 ふぞろいな合格答案エビソード11
前半に再現答案が事例Ⅰ~Ⅳと掲載されており、後半には合格者のインタビュー形式試験問題に対する80分間のドキュメントと再現答案が掲載されております。
受験生のバイブル。
今年2020年4月には早々と編集した総集編が登場。
2018年と2019年のふぞろいの前半の合格答案部分をまとめた書籍です。
自分は掲載されている答案を1つの模範解答として活用しました。
2018年と2019年のふぞろいの後半の80分間のドキュメントと再現答案がまとめられた書籍です。
事例問題攻略マスター
再現答案やプロセスではお薦めです。
今年5月に新刊が発売されました。
各事例の解き方と令和1年(2019年)~平成27年(2015年)までの過去5年分の過去問の解説付き。書籍がA4版と小さ目で持ち運びに便利。
ある優秀な人の解答として参考にしました。
TBC速習2次過去問題集 平成28~30年度 ¥4,180
本日のまとめ
- 解答作成の前に俯瞰して全体を見る目、鳥の目が必要です。
- SWOT分析は、S強みO機会を赤オレンジ黄色の暖色系、W弱みT脅威を青・水色の寒色系のマーカーで色づけて視覚的に判断。
- 難しい問題にはまって考え過ぎてしまうと、バランスを崩してタイムオーバー。
- 解きやすい問題から解いて先行逃げ切り型が理想。
あれっ。答え書いてないじゃん。解答が公表されていないのが2次試験なんです。
私のブログも解答は公表しないいんです。
いやいや、作成した解答まで載せようとも思い受験校の解答や各種ブログ等で掲載している解答を見直しまとめようとしました。
しかしながら色々な方向性がありまとめられなかった。
今回は解答は割愛します。
まずは解答プロセスに従って考えて実践してみてください。
※2次試験対策の記事は、複数年に渡り学習したきた自らの記録、各種学習参考書や過去問解説の情報、 勉強会や学習仲間とのやりとり、ブログなどさまざまな情報を元に、改めて2次試験の問題を振り返り受験生の勉強の参考になればと思い記事にさせて頂いております。
※いいねと思った方は、ポチってください。
中小企業診断士登録証をオリジナルバナーにしました。
令和2年5月1日の登録ではなく、令和2年5月20日の登録でした。





